前回の記事では、株式会社インテリアホソイが大切にする“お客様の声が聞こえる仕事作り”についてご紹介しました。では、どうしてその考えに至ったのでしょうか。経営難の“暗黒の時代”を経験した細井社長が、苦境を乗り越えて新たなビジネスモデルへ踏み出した背景とは──。その切実な体験談を交えながら、内装業界だけでなく私たちの働き方にも通じるヒントを紐解いていきます。
細井 和博(ほそい かずひろ)
株式会社インテリアホソイ 代表取締役
前回の記事はこちら
厳しい経営状況を乗り越え、“お客様の声”に行き着くまで

前回の取材では「お客様の声が聞こえる仕事作り」についてお話しいただきました。もう少し当時の状況を深掘りしたいのですが、初めはどんな状態だったのでしょうか?

21歳の頃から父の内装会社を手伝い始めたのですが、最初は経営がうまくいかず、借金取りが押しかけてくるような状況でした。夢とかビジョンというものはほとんどなくて、27歳くらいまでは「今月をどう乗り切るか」ばかり考えていたんです。
正直、自分の給料も取れない状態で、小遣い3万円ほどでずっと働いていました。これが私にとっての“暗黒の時代”で、今でも「絶対にあの頃には戻りたくない」という思いは強く残っています。

それは相当厳しい状態ですね。そこから、どのように状況が変わっていったのでしょうか?

これは前回もお話ししましたが、大きな転機は38歳の頃、初めて元請けでホテルの改装工事を担当したことです。普段は下請けとして工務店さんの下で仕事をしていたので、お客様の声はほとんど私たちには届きませんでした。ところが元請けになると、お客様と直接やりとりできる立場になります。
工事が終わって引き渡しの時、お客様が本当に喜んでくださって「ありがとうございます!」と感謝の言葉をいただいたんです。その瞬間はとっさに「私たちができる仕事をしただけですよ」と返してしまったんですが、家に帰ってからも翌日になっても、いつになく気持ちがよかった。それまで朝早くから夜遅くまで働いてきつい仕事でしたが、“お客様が喜んでくれる”ことが、こんなにやりがいになるのかと感じたのを覚えています。
そう思うと、「仕事のやり方を変えることで、お客様にもっと喜んでもらえるし、その姿を見れば自分たちのモチベーションも高まるんじゃないか」と考えるようになりました。大変な仕上げ作業や長い労働時間も、“やりがい”があればカバーできるかもしれない、と。

その経験が、仕事に対する考え方を大きく変えたのですね。

その仕事がきっかけで、「もっとお客様の声が聞こえる仕事がしたい」と思うようになりました。そして39歳の時、京都中小企業家同友会に入会し、経営を本格的に学び始めたんです。そこで経営理念を作り、会社としての方向性を定めるなかで「お客様の声を聞ける仕事をもっと増やそう」と決意しました。

具体的にどのような取り組みに変わっていったのでしょうか。

2016年にショールームを作り、デザインから施工、アフターサービスまで自社内で完結できる体制を整えました。通常の内装下請工事店は、大部分を外注に回すところが多いです。でも私たちは自分たちでデザイナーを雇用し、職人も育てる。もちろんコストはかかりますが、こうしなければこの仕事は面白くならないと思いました。
もしこの取り組みがうまく軌道に乗れば、業界の若い人たちが憧れる一つのモデルになるかもしれない。建設業界は3K(きつい・汚い・危険)と言われて若い人が避けがちですが、実際はやりがいのある、かっこいい仕事です。それを証明するには、まず自分たちが働き方を変え、お客様の声を直接聞ける仕組みを作る必要があると考えたんです。

ビジネスモデルを変えただけでなく、仕事の姿勢そのものも変えたんですね。なかでも特に意識されていることはなんでしょうか?

世間ではよく「お客様の目線で」「お客様の身になって」と言いますが、それだけだと表面的な話に留まりがちです。私は“お客様になりきる”ことが大切だと考えています。もし自分がお客様だったら、リスクやネガティブな面も含めて「正直に全部伝えてほしい」だろうな、と。そうやって自分自身がお客様になりきることで、本当に求めていることを見極められるし、やがて「全部任せよう」と思っていただける関係が築けるんです。
よくあるのが「クレームを出さないように仕事しよう」と、ただ怒られないことを目指すパターン。でも、それでは楽しくありません。面倒な問題や課題を避けるのではなく、正面から乗り越えることで新しい景色が見えてくる。それが成長だと思っています。
私自身、数えきれないほどの山を越えてきました。だから、新しい山が現れても「その先にはきっとまた新しい景色がある」と考えて進めるようになりました。

職人の誇りを支え、未来を築く──変わりゆく内装業の姿

今回のテーマである「京都経営者の哲学」について、細井社長が大切にされている考えはなんでしょうか?

やはり先ほどお話しした経営理念ですね。制定以降ずっと大切にしています。会社がある限り追い求め続ける“社是”のような存在です。たとえ100年、200年経っても変わらず受け継がれていくものですね。
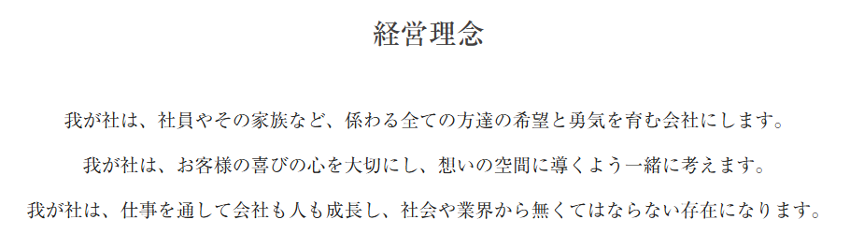

経営理念を考えられる際、どんなことを特に重視されたのでしょうか?

大きく3つあります。
1つ目は、社員さんの働きがいです。社員さんとその家族が希望や勇気を持てる会社でありたい。
2つ目は、お客様の満足を追求すること。お客様が「住みたい」「働きたい」と思う空間を一緒に考え、作り上げることです。
3つ目が、私の中では実は最優先かもしれませんが、内装業界の発展、特に職人さんの地位向上ですね。

前回の取材で、建設業はピラミッド型の構造になっていて29種類ある専門業のうち、内装は一つの建築物のコストに占める割合が1パーセントほどしかないために地位が低くなってしまうことを教えていただきました。

そうなんです。特に現場で働く職人さんは自分で仕事を選ぶことができず、頼まれた仕事を断るかどうかぐらいしか意思を示せない。そんな環境では、ずっと虐げられたままになってしまいます。

たしかに、内装業界の厳しい構造が垣間見えます。細井社長は具体的にどう変えようとしているのですか?

たとえば当社では、半年に1回PR誌(https://www.inxkyoto.co.jp/hot/)を無料で発行しています。そこでは若い社員が中心となって、職人さんの1日を密着取材したり、現場の様子を紹介したりしているんです。一見すると売上に直結しづらい活動に見えますし、どれだけ集客につながっているかも分かりません。
しかし、客観的に自分たちの仕事を見直すことで、「こんなにすごいことをしているんだ」と職人さん自身が気付くきっかけになる。そして何より、まだこの業界に興味を持っていない若い人たちに、職人の仕事のカッコよさを伝えることができる。その意義は非常に大きいと思っています。

業界全体のことを考えた取り組みなんですね。

自分たちの会社の発展だけを考えるのであれば、建築や不動産も扱えるようになった方が早く結果が出ると思うのですが……。でも、それだと“内装業界そのもの”を変えたことにはならないですよね。私はあくまで“内装工事店”というポジションで、デザイン・施工・アフターまで一貫して内製化するモデルを確立したいんです。
なぜなら、若い内装屋さんが「将来はあの会社のようになりたい」と思えるような目標が、今の業界にはほとんど存在しないんです。だからこそ私たちが先陣を切ってチャレンジして、もしこれがうまくいけば業界全体の未来が変わるかもしれない。それくらいの覚悟でやっています。

20代のうちに“価値観の違い”を楽しもう

最後に、就職活動中の学生や、京都での活躍を目指す20代の若者に向けてメッセージをお願いいたします。

人それぞれですが、私がいちばん伝えたいのは「価値観の違う人たちとの関わりを怖がらない」ということです。価値観の似た人といるのは居心地が良いですが、それでは大きな刺激がありません。むしろ「絶対に自分とは違う」と思うタイプの人こそ、人生を豊かにしてくれる存在になるんです。
今の若い社員と接していても、世代間ギャップを感じることは多いんですが、私自身そこから学ぶことも本当に多いんです。違いを面倒くさいと思って避けるか、それとも自分の成長につなげるか。どう受け取るかで結果はまったく変わってきます。

価値観の違う人と出会うといっても、具体的にはどうすればいいのでしょうか?

いまはSNSやオンライン交流会など、さまざまな方法で新しいコミュニティに出会えます。大学や会社以外の活動、たとえば異業種交流会や地元のボランティア、趣味のサークルに顔を出すのもいいでしょう。大事なのは、普段の生活では会わない人たちと接点を持つことです。
さらに余裕があれば、海外旅行にチャレンジしてみるのもおすすめです。特に発展途上国など、日本とはまるで環境が違う場所に行くと、自分の“当たり前”がひっくり返される経験ができます。そこには、言葉も文化も考え方も違う人々がいて、一気に視野が広がります。

その気になれば、違うコミュニティや環境にいつでも踏み出せるんですね。

そうですね。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、価値観の合わない人とあえて話してみたり、文化が異なる場所に飛び込んでみたりすることで、自分でも気づかなかった可能性を発見できるはずです。
結局、たくさん経験した人ほど、いざというときに判断の幅が広がるんです。小さな迷いやトラブルを何度も乗り越えるうちに、「こういう山なら自分にも越えられる」という自信が生まれてくる。
特に20代のうちは、失敗しても大きなリスクにつながりにくい時期ですから、むしろ“経験を積むこと”を最優先に考えてほしい。そして、そこにこそ新しい価値観や人脈、成長のチャンスが詰まっています。
私自身もまだまだ勉強中ですが、価値観の違う人と出会うたびに、新しい景色が広がる手応えを感じています。若い皆さんには、ぜひその一歩を踏み出してもらいたいですね。

<取材・執筆=日野、写真=田部>
株式会社インテリアホソイ HP:https://www.inxkyoto.co.jp/
